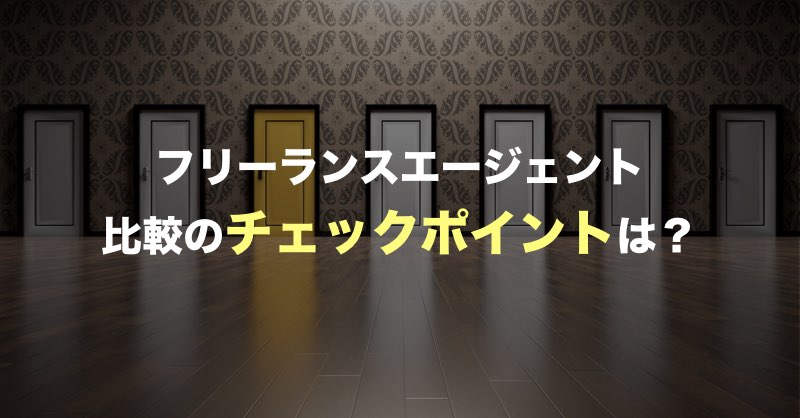こんにちは。Enjoy IT Life管理人の仁科(@nishina555)です。
フリーランスエンジニアの方の中で案件を探すにあたりフリーランスエージェントを利用される方も多いと思います。
この記事を執筆しているぼくはWebエンジニアとして5年キャリアをつみ、2019年4月にフリーランスエンジニアへキャリアチェンジしたのですが、はじめての案件探しはフリーランスエージェントを利用しました。
しかし、いざフリーランスエージェントを利用しようと思っても、大小合わせてその数はとてもたくさんあり、どこのフリーランスエージェントを利用すればいいか分からないという人も多いのではないでしょうか。
いまでは『オススメ フリーランスエージェント』などと調べれば、オススメフリーランスエージェントに関する情報をたくさん見つけることができます。
しかし、フリーランスエージェントによって特徴や得意分野は異なります。また、人によって案件探しで重視するポイントは異なるはずです。
ですので、『万人に対してオススメのフリーランスエージェントはここ!と一概には言えない』というのが複数のフリーランスエージェントを利用してきたぼくの結論です。
自分に適したフリーランスエージェントはできれば自分で見つけられるようになったほうがいいですね。
とはいえ、『どういった観点で比較するとフリーランスエージェントの特徴がわかるのか』『どうやったら自分に適したフリーランスエージェントを見つけられるか』などについては、フリーランスエージェントをあまり利用したことがない人にとってはピンとこない事かと思います。
そこで今回は10社以上フリーランスエージェントを利用してきたぼくの経験談をもとに、フリーランスエージェントを比較するためのチェックポイントを紹介したいと思います。

こんなことを考えている方の参考になればと思います。
フリーランスエージェントを比較する際のチェックポイントまとめ
まずはじめにフリーランスエージェントを比較する際のチェックポイント一覧を紹介します。
フリーランスエージェントを比較する際は以下のチェックポイントに注目するとよいと思います。
- 得意な案件のジャンル
- 扱ってる案件の稼働日数
- 保障制度
- 支払いサイト
- 平均単価
- 担当者の特徴や相性
以下ではそれぞれのチェックポイントについて紹介したいと思います。
得意な案件のジャンル: Web案件が得意か、SE案件が得意か
得意な案件のジャンルはフリーランスエージェントの特徴がでる要素の1つです。
フリーランスエージェントが扱う案件の種類や得意なジャンルは運営会社に依るところが大きいです。
誤解を恐れずにいうと、人材系の会社が運営しているフリーランスエージェントであればWeb系、SIerが運営しているフリーランスエージェントであればSE案件を得意としています。
とはいえ、ある程度の規模のフリーランスエージェントであればWeb案件もSE案件も両方揃えているところがほとんどです。
特にWeb案件は時代的な流行りもありますし、基本的にはどのフリーランスエージェントでも十分な案件数があると思って差し支えはありません。
注意するとしたら、最近サービスをはじめたばかりの小規模なフリーランスエージェントの場合ですとSE案件は取り扱っていないというケースがあるということです。
そういった意味ではSE案件を探すのであれば歴史のある大手フリーランスエージェントがよいでしょう。
扱ってる案件の稼働日数: 週5日常駐案件のみを扱うのか、週5日未満の案件も扱うのか
フリーランスエージェント経由で案件を探す場合、基本的は週5日常駐案件が前提となっております。
ですので、 週5日未満の稼働を希望している場合は、フリーランスエージェントが週5日常駐以外の案件も用意しているかチェックをしておくとよいでしょう。
とはいえ、フリーランスエージェントのWebサイトに『週5日未満案件あり!』と書いてあっても、実際にフリーランスエージェントのところへ話を聞きに行くと「いまは週5日未満の案件はないんですよねー」といわれるケースが少なくありません。
ですので、もし週5日常駐以外の案件を探す前提であれば、週5日未満の案件も扱うフリーランスエージェントに登録をしつつ、並行して個人で営業活動を進めるという方法がオススメです。
もしくは、数こそ少ないですが、週5日未満の案件を中心に扱うWorkship AGENT![]() のような特化型のフリーランスエージェントを利用するという方法もありだと思います。
のような特化型のフリーランスエージェントを利用するという方法もありだと思います。
保障制度: サポート対応、福利厚生、補償制度はどういったものがあるか
フリーランスエージェントでは案件に参画中のフリーランスエンジニアに対して様々な保障を用意しているところがあります。
保障をカテゴリ分けをすると主に以下の3つに分けられます。
- 案件参画中のカウンセリングやキャリア相談などの『サポート対応』
- リロクラブ、ベネフィットワンなどの『福利厚生サービスの利用』
- 書籍費用、交通費、保険費用などの『金銭面の補償』
自分がフリーランスエンジニアとして活動していくにあたり、『どういった出費が考えられるか』『どういった保障があると助かるか』というのを考えておくとよいでしょう。
なお、複数のフリーランスエージェント経由でオファーをもらったぼくの実績をもとにはなしをすると、『サポートが手厚い = 人件費やコストがかかるので単価が低くなる』とは一概には言えません。
ですので、どのフリーランスエージェント経由で案件に参画するかは『最終的に提示された単価』と『フリーランスエージェントの保障制度』のバランスなのかなと思います。
保障制度だけでフリーランスエージェントの善し悪しは判断できませんが、保障制度はフリーランスエージェントの特徴が出やすい要素なので注目してみてみるとよいでしょう。
支払いサイト: 早いところは15日、遅いところは40日~60日
支払いサイトとは、稼働実績を締めてから報酬として振り込まれるまでの期間のことをいいます。
支払いサイトは早いところだと15日、遅いところだと40日~60日となっております。
支払いサイトが遅いと、長期に渡り報酬が振り込まないことになります。ですので、特にフリーランスになりたての人にとっては支払いサイトが早いに越したことはないです。
とはいえ、初めての報酬が振り込まれてからは1ヶ月おきに定期的に振込がされるので、支払いサイトの期間の長さが気になるのは参画した案件で初めて報酬がもらえるまでの期間だけです。
手元にお金がないのですぐに報酬が欲しいという人は支払いサイトをしっかりとチェックしておくべきですが、そうでなければそこまで厳密にチェックするべき項目ではないかもしれません。
フリーランスエージェントを決める際には、『報酬の振り込まれない期間を自分はどこまで許容できるか』を事前に把握しておくことをオススメします。
平均単価: 平均年収を公表していればチェックする
単価は高いに越したことはないですよね。特に、収入を増やすためにフリーランスエンジニアになった人にとっては単価は重要なチェックポイントです。
基本的にはスキルが高いほど単価はあがりますので、技術力をあげることで高単価を目指すことができます。
しかし、単価を決める要素はエンジニアのスキルを含め、以下のようなものが考えられます。
- エンジニアのスキル
- スキルの需要
- クライアントの予算
- フリーランスエージェントのマージン率
つまり、同じスキルセットでも案件との相性次第で単価をアップさせることは可能です。そして、どれだけ高単価で交渉できるかがフリーランスエージェントの仕事であり、担当者の腕の見せ所でもあります。
ですので、フリーランスエージェントを利用するエンジニアの平均単価・年収もチェックしておくとよいでしょう。
調べ方ですが、一番ベストな方法は実際に複数のフリーランスエージェント経由でオファーをもらい、フリーランスエージェント別で平均オファー単価を比較することだと思いますが、時間的に大変かもしれません。
ですので、フリーランスエージェントのWebサイトの情報を調べたり、キャリアカウンセリングのときに単価の相場感を聞いたりするのが現実的でオススメな方法です。
ただし、ネットの情報やキャリアカウンセリングの回答はあくまで『平均』『目安』ですので、参考程度にとどめておきましょう。
例えば、とても年収の高い層が平均年収を押し上げる可能性もありますし、あえて相場よりも高めの単価を提示することで注目してもらう営業トークかもしれません。
とはいえ、ある程度単価の相場感もわかりますし、高単価を実現できる自信がないフリーランスエージェントは単価の話をそこまでしたがらないので、聞く価値のあるチェックポイントだと思います。
担当者の特徴や相性: 技術に詳しい、連絡が丁寧、など
フリーランスエージェントを選ぶにあたり、案件を紹介してくれる担当者との相性も大事になってきます。
ネットの情報などから各フリーランスエージェントの担当者の特徴をある程度知ることはできるかもしれませんが、こればかりは実際にフリーランスエージェントに足を運んでみたり、案件を紹介してもらったりしないと分からない部分が多いです。
よく話題にあがるのは『担当者が技術にどれくらい精通しているか』という点ではないでしょうか。
技術の理解度に関しては、『大手になればなるほど案件紹介の対応がマニュアル化されるため、担当者に技術的な専門性を求めるのは少し厳しい』というのが個人的な意見です。
ですので、『技術について全然わかってなくて案件紹介もままならない』というような状況になることはないですし、ぼくもそのような経験はありません。
技術の理解度のほかにも、『性格的な相性』や『案件紹介の進め方の相性』など色々な相性があると思います。
複数の担当者と同時並行でやりとりすることで『自分と相性のいい担当者』『(言い方が悪いですが)手際の悪い担当者』というのがわかってきます。
ですので、相性のいい担当者を見つけるという意味でもいくつかフリーランスエージェントに登録することはオススメです。
例えば、ぼくの場合ですと、ぼくはメールをなるべく早く返してもらいたいと思うタイプなのですが、複数のフリーランスエージェントと同時並行でやり取りをしていたので、どのフリーランスエージェントの担当者が連絡が早いのかということを相対的に比較することができました。
もちろん、フリーランスエージェントを1つに絞って、『もし担当者と相性が悪ければ、担当者を変えてもらう』という方法もアリです。
しかし、フリーランスエージェントとのやりとりは基本的には担当者が窓口になっているため、担当者を変えてもらいたいと本人に直接言うことになってしまいますし、そもそも変更できるかどうかはフリーランスエージェントによって対応が異なります。
担当者との相性がありますので、いきなり利用するフリーランスエージェントを1つに絞るのでなく、気になったフリーランスエージェントのところへはとりあえず話を聞きに行ってみるというフットワークの軽さも大切だと思います。
大切だと思うけどフリーランスエージェントの比較のチェックポイントから除いた項目
ここまででフリーランスエージェントを比較する上で大切になるチェックポイントについて紹介をしました。
ここからは『フリーランスエージェントを比較する際に重要なチェックポイントになりえそうだけど、個人的には不要だと思ったもの』について紹介をしたいと思います。
案件数: ある程度の案件数があればそれで十分
案件数は多くのフリーランスエージェントでアピールをしている点ですし、多いに越したことはありません。
たしかに、設立されたばかりで実績もほとんどないようなフリーランスエージェントを利用する場合や、マイナーなスキルセットで案件を探す場合、希望条件が特殊(週2日で働きたい、リモートワークで働きたい、など)でしたら、案件数を気にした方がいいかもしれません。
しかし、一般的なエンジニア・フリーランスエージェントであれば、ある程度案件数があれば自分の希望条件にマッチした案件を見つけることはできる、というのがぼくの意見です。
少なくとも、ぼくが今までに利用してきたフリーランスエージェントでは希望条件にマッチした案件が全くなくて話が進まなかったという経験をしたことはありません。
ですので、案件数についてはそこまで気にする必要はないと思います。
マージン率: マージン率は原則非公開なので比較できない

フリーランスエージェントを利用するフリーランスエンジニアであれば誰しもが思うことですよね。
実際ぼくもフリーランスエージェントを利用するときはマージン率はかなり気にしていました。
ただ、『マージン率』というのは人材紹介を行なうフリーランスエージェントにとって、とても重要な情報です。そのため、ほとんどのフリーランスエージェントではマージン率を非公開にしています。
ぼくはマージン率を教えてもらうために、フリーランスエージェントのキャリアカウンセリングを受けた際はマージン率について毎回のように質問をしていたのですが、どこのフリーランスエージェントでも「一般的なフリーランスエージェントよりも低いと評判です」とお茶を濁されるのが関の山でした。
Webサイトでマージン率を公表しているフリーランスエージェントはMidworks(ミッドワークス)![]() (10%~15%)やPE-BANK
(10%~15%)やPE-BANK![]() (8%~12%)くらいでしょうか。1
(8%~12%)くらいでしょうか。1
ネットでは『マージン率が低いフリーランスエージェントランキング』や『マージン率が低いフリーランスエージェント一覧』といった記事をよく見かけますが、ほとんどのフリーランスエージェントがマージン率を非公開にしているので、憶測で書かれた信用できない情報だとぼくは思っています。
フリーランスエージェントのマージン率は原則非公開ですので、チェックする必要はないというのがぼくの意見です。
仮に他社と比べて極端にマージンを取っているフリーランスエージェントが存在した場合、そのフリーランスエージェントがエンジニアへ提案する単価はマージンを多く取っている分、他社と比べて低くなります。
そうなると、マージン率の高いフリーランスエージェントを利用するエンジニアは自ずと減っていき、フリーランスエージェントは自然消滅していくはずです。
つまり、極端にマージン率が高いとそもそもフリーランスエージェントはサービスを継続できないわけですから、フリーランスエージェントごとでマージン率が極端に違うということは考えにくいです。
ですので、繰り返しにはなりますが、マージン率に関してはそこまで気にする必要はないでしょう。
まとめ
以上でフリーランスエージェントを比較する際のチェックポイントの紹介を終わります。
フリーランスエージェントを比較する際のチェックポイントは以下のようになります。
- 得意な案件のジャンル
- 扱ってる案件の稼働日数
- 保障制度
- 支払いサイト
- 平均単価
- 担当者の特徴や相性
どのフリーランスエージェントを利用しようか考えている方の参考になればと思います。
なお、ぼくが利用したフリーランスエージェントの一覧は『オファー実績のある現役利用者だから分かる!フリーランスエンジニア向けエージェント比較まとめ』で紹介していますので、こちらも参考にしていただければと思います。
この記事がいいなと思いましたらツイッター(@nishina555)のフォローもよろしくお願いします!