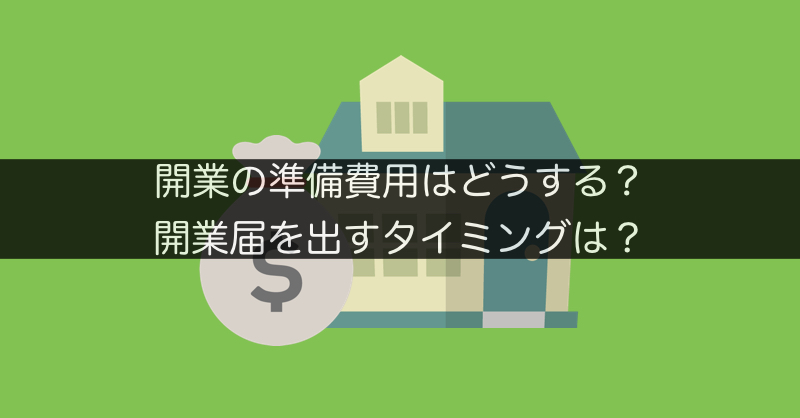こんにちは。仁科(@nishina555)です。
会社員からフリーランスになることを考えている場合、退職してから「さて、フリーランスの準備をしよう!」という人は少ないと思います。
ほとんどの人が会社員の時から少しずつフリーランスに向けた開業の準備をしていき、環境が整い始めた段階でフリーランスに転身をする、という流れだと思います。
会社員の時に開業の準備をしていると感じる以下のような疑問に答えたいと思います。
「開業届はまだ出してないけど、開業準備の費用は経費になるのかな?」「開業ってどのタイミングでするのが適切なんだろう?準備を始めてから?事業開始してから?」
はじめに結論をいってしまうと、開業の準備費用は開業費として償却できるので、退職してから開業届を出せば大丈夫です。
以下では開業届や開業費について詳しく説明をしていきます。
目次
開業届について
開業届は事業開始から1ヶ月以内に税務署に提出をするもので、開業に費用はかかりません。
また、開業届に提出義務はなく、提出しないと罰則を受けるものではありません。
しかし、開業届を出すことでフリーランスとして働くためのメリットを受ける権利を得られるので、開業1年目から開業届は出しておくといいです。
開業届の提出手順については以下の記事で紹介をしております。
なお、開業届を提出することで得られる主なメリットは以下です。
- 青色申告できる
- 小規模企業共済に加入できる
- 屋号で銀行口座を開設できる
メリットについて詳しく説明します。
青色申告できる
確定申告の方法白色申告と青色申告があります。
青色申告のメリットは色々ありますが、控除額が白色申告と比べて大きいのでより節税できるというのが一番のメリットです。
注意点としては、青色申告承認申請書は開業日(事業を開始した日)から2ヶ月以内に提出しないといけないという点です。
ですので、青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出をして、青色申告承認申請書の提出日が開業日の2ヶ月以内になるように調整をしておきましょう。
小規模企業共済
小規模企業共済は個人事業主のための退職金のようなもので、掛金を毎月積み立てていきます。小規模企業共済の掛金は所得控除になるため、節税しながら将来のための貯蓄ができるというメリットがあります。
掛金は1,000円から70,000円の間を500円単位で自由に選択できます。
なお、受給額は掛金の80%から120%の額となっており、割合は掛金の納付月数に応じて決まります。
小規模企業共済の受給については細かく設定されていますが、
20年以内に任意解約をすると、掛けたお金が全額は戻ってこないという点は覚えておくといいでしょう。
屋号で銀行口座を開設できる
事業を開始したらプライベート用と事業用で銀行口座を分けておくと、収入や経費がわかりやすくなるため確定申告が楽になります。
開業届を出す際に屋号名も決めていた場合、事業用の口座を屋号名で開設できるようになります。
もちろん、個人名義の口座を二つ用意し、それぞれをプライベート用と事業用で分けても問題ありません。
開業届を提出する前までにかかった準備費用はどうなる?
開業届と青色申告承認申請書を提出し、事業所得として認められれば青色申告ができるようになります。
開業日以降であれば経費として処理することになります。
では、開業日以前の「まだ事業を始めていない時期に利用した準備費用」の処理はどうなるのでしょうか?
実は、会社員の時にフリーランスになるための準備費用は開業費という事業費用として扱われます。
開業費として扱われるものとしては以下のようなものがあります。
- チラシなどの広告宣伝費
- Webサイト作成費用
- 文房具などの事務用消耗品費用
- 書籍などの資料代
- 打ち合わせのための会議費用
- 名刺や印鑑の購入費用
- オフィスの契約費や改装費
あくまで開業のために利用したものに限るということを忘れないでください。
準備費用を開業費にするためにも、開業を考え始めたら会社員の時から領収書などは忘れないで取っておきましょう。
ただし、開業費を考える上で以下の2点について注意する必要があります。
- 総額が10万円以上であれば開業費として繰延資産に認められる
- 単価が10万円以上であれば繰延資産ではなく固定資産
これらについて詳しく説明していきます。
総額が10万円以上であれば開業費として繰延資産に認められる
総額が10万円以上であった場合、開業費として扱われます。
開業費は経費ではなく繰延資産という資産に分類されます。
資産として開業費が処理しされ、その後経費計上していきます(償却)。
開業費の償却は以下のような方法で処理されます。
- 均等償却
- 任意償却
一方、任意償却とした場合には、所得の少ない年には償却費用を少なくし、所得が多い年には償却費用を多くするといったことができます。
つまり、所得がそれほど高くない時(税率が低い時)は償却をせず、所得が高い時(税率が高い時)に償却をするといったことが任意償却では可能になり、効率よく節税対策ができます。
任意償却は経費では行えないため、開業費として認められた場合のメリットと言えます。
もし合計が10万円未満の場合は開業日の日付でそれぞれの費用を該当する勘定科目として経費計上することになります。
単価が10万円以上であれば繰延資産ではなく固定資産
パソコンや机、イス、車といったように単価が10万円以上のものについては、開業費ではなく固定資産として扱われます。
固定資産は、国で決められている耐用年数に従い、定率(定額)で減価償却を行ないます。
この特例を活用すれば、30万円未満までであれば減価償却をせず全額まとめて経費計上できるようになります。
例えばパソコン本体の耐用年数は4年なのですが、少額減価償却資産の特例を活用したとします。
30万未満のパソコンであれば4年を待たずに全額経費計上できます。
開業費は開業日からどれくらい前のものが適用可能?
開業費にできる期間については決まったルールはありません。
ですので、常識的に考えて妥当だと思う期間を開業期間として設定します。
色々な意見をみてみるとだいたい3ヶ月から半年、長くても1年くらいが妥当なようです。
あまりに期間が長いものは税務調査でチェックが入る可能性があるのでほどほどにしておきましょう。
開業届前に収入がある場合はどうすればいいの?
収入がある程度増えてきて安定したから開業届を出すというのは当然の流れです。
そうすると、開業日以前に収入が発生している場合があります。
開業日前の収入は開業届と青色申告出すことで事業所得として認められることがほとんどです。
気になるようでしたら税務署で確認するのが一番確実なので、相談をしてみるとよいでしょう。
まとめ
今回は開業準備の費用の処理の仕方と開業届について説明をしました。
会社員の時に開業準備をしている場合、開業準備にかかった費用の領収書はちゃんととっておき、退職してから開業届と青色申告承認申請書を出す、という流れでいいでしょう。
もし、会社員のときから会社の給料以外の収入が発生していた場合は確定申告の際に申請を忘れないようにしましょう。
なお、開業届と青色申告承認申請書の提出は開業freeeを活用すれば、3ステップに沿って必要事項を記入していくだけで、必要書類が完成できます。
実際に開業freeeを利用した時の手順などについては以下の記事で紹介をしているので興味のある方はご覧になってください。